「気」の働かせ方について
いよいよ今年は6段挑戦の年となります。
5段に昇段させていただいてから早くも5年の月日が経とうとしている・・・。
「光陰矢のごとし」とはよく言ったものだと思います。
さて先日、これまで自分が残してきた記録をまとめて読み返していて、面白いことを発見しました。ちょうど昨年2月の中頃に下記のような記事を残していたようなのです。
その記事には、一昨年取り組んでいた課題である「足と腰で行う剣道〜先を取る」がひと区切りつきそうな所で新たな壁にぶつかって悩んでいた私が、その壁を乗り越えるためのヒントになりそうな課題について、一時期に何人かの先生に同様の指摘を立て続けに受け、昨年のテーマを「間合を知ろう!」に決めたという件を書いています。
すると、大変興味深いことに、今年の同じ2月中頃、下記のような記事を書いていたのです。
ここには、九州松下剣友会の稽古会で新しい課題を指摘されてありがたかったということが書かれています。
この「指摘」は、昨年の課題であった「間合を知ろう!」がある程度区切りがついた所で次の「目に見えない壁」にぶつかって悩んでいた私の意表をついて突きつけられたもので、言われたその場では何を言われたか実はよくわかりませんでした。
その晩よくよく考えてみても何を言われているのかわからなかったくらいで、翌日のむさし剣錬会朝稽古でもう一度その話について聞かせてくださいとお願いしたくらいのものでした。
ところが、この指摘を受けた直後に、別の先生から立て続けに全く同じ指摘を受けたのでした。
その後は、考えれば考えるほど、これこそ今の自分が直面している壁を乗り越えるために必要な課題そのものなのではないかという確信を持ちはじめ、とうとう今年のテーマを「気の働かせ方を学ぼう!」に決めたところだったのです。
そのお礼を下記の記事中の「追伸」に書いていたりしています。
後から考えると、この流れは、まるで昨年の繰り返し・・・違うのは課題の中身だけでした。
不思議なものですね(*^_^*)「求めよ、さらば与えられん。」を体感した出来事でした。
さて、肝心の「気」の働かせ方について考えて見ましょう。
指摘を受けた内容をまとめるとこういう感じでした。
・ 自分が打とうと思うときにしか攻めていかない(攻めてこない)。
・ 自分が打とうと思ったときにしか打っていかない(打ってこない)。
・ 相手不在の剣道で自分勝手になっている。
・ 「虚」と「実」のコントロールができていない。
・ 心が「実」の時は強いが「虚」の時は赤子の手をひねるほどに造作もない。
「先」を取り「間合」を知り「一拍子」で打突する。
ようやくそのイメージが持てるような気になってきた矢先の文字通り「意表をつかれた」指摘でした。
あまりにもピンとこなかったため、その夜はあまり眠れませんでした(*^_^*)
なぜだぁ〜!!!と悶々と考え続けて・・・そしてようやく思い当たりました。
相手の「気」を無視していると言うことか?「合気」になれていないということか?さらに言うと「気」にムラがあるということか!?
まとめると「気」を上手に働かすことができていないと言うことなのではないだろうか。
つまり、相手の「気」と無関係かつムラがあるから、そこにはたっぷり「油断」がある。つけいる「隙」がある。「虚」になる瞬間がある。
これは心の問題だ。そうとわかれば、次に考えるべきは、これを克服するにはどうすればよいかだ!というわけで、ここでようやくチャレンジャーの精神に戻ることができました。
そういうわけで今年は一念発起、新たな気持ちで次の段階を目指すことにいたします。
まずは「相手あっての剣道」いわゆる「合気」を体感できることから始めて、「気」を自由自在に働かせることを目指してみようと思います。
よくよく考えてみると、実はこれはかなり以前から色々な先生や先輩から指摘され、すでにどっぷり抱えていたテーマで、正直これまでは高度すぎて実感がもてないまま放置していたものでした。ですから、取り組むにはいい機会なのです!
相手の「気」とこちらの「気」のチューニング作業から初めて、きちんと周波数が合ったところで心のやり取りを行う。
何はともあれこの辺からの取り組みになると思います。相手の「気」を感じ取れない鈍感さ加減では話にならないでしょう。
そう考えていくと、今の自分がどれだけ無神経な剣道を展開しているかを認識して恥ずかしくなってき始めます。
とりあえず、一連の流れのイメージとしては・・・
場を支配すべく丹田で練った「気」を周囲に解き放つ。
相手の「気」を感じ取り、こちらの「気」との間にせめぎあいが起きるのを確認してから心のやり取りを始める。
相手の心を自分の心に写し取ることができるかどうか「不動心」の勝負。
上手・下手に関わらず「懸かる稽古」を旨として打太刀の気概で「機」を見てこちらから積極的に打ち間に入っていく。
打つために「打ち間」に入るのでなく、いつでも打てる準備ができたと感じたら、自ら進んで、ただ「打ち間」に入っていく。
そこで相手がどんな動きを起こそうとも「間髪容れず」に技を発動し相手の心の「虚」に向けて打突を放つ。
このようなイメージの状態から繰り出される「究極の一本」を目指して試行錯誤する。
例え一刀両断されても悔いは無いという「捨て身」の覚悟で「四戒」を払って迷い無く打って出る。
実際に打たれれば、そこは捨て所ではなかったことを教えられたも同然で、すかさず感謝する。
実際に打てれば、自分に至らぬところは本当に無かったかと、すかさず反省する。
立会いの間中、そんな「油断も隙も無い状態」に自分を保ち続ける。
イメージするところからはじめるしかないですから、まずはここからやってみようと思います。
テーマは「厳しい剣道」です。
ちなみに、自分は本当に「気」を十分に働かせることができるようになれるのか?
この問題に関しては人間の思考に関するひとつの仮説があります。
****************************************************************
そうできるようになれると思えばそうなれるし、
そうできるようになれないと思えばそうなれない。
いずれにせよ、なんにせよ、思ったとおりになる。
****************************************************************
私は経験上これは限りなく真理に近いものではないかと考えて信じて活用していますので、今回もこの「理」でまい進します。
『為せば成る 為さねば成らぬ なにごとも 成らぬは人の為さぬなりけり』
の精神でがんばります(*^_^*)
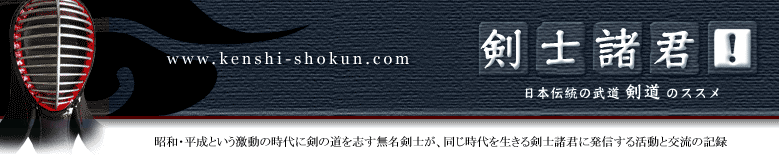
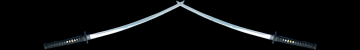
コメント
こんにちは、わたしは大学で柔道をやっています。剣道に関係なくてすみません。今、この文章を拝見さして頂きましたが、柔道の場合は相手の合気を考える必要があるのか、柔道も上のような概念が必要なのか疑問に思いました。先輩にはとにかく、いい組み手になったらすぐにしかけろと言われていますが、剣道でも似たような事(よい間合い?)はあるのですか。
投稿者: ソリッド スネーク | 2009年09月03日 20:53
海外で昨年から剣道を始めた40歳の主婦です。
最近6級をとり、来年には4級まで頑張りたいと思っています。同じぐらいのレベルの人と地稽古の時、小手は打てるようになったのですが、
面がなかなかとれません。どうすれば、面を打てるようになれるのでしょうか? それと踏み込みがいまいちできないし、切り替えしの時、足の方が早くでてしまいます。
何かいいアドバイスお願いします。
投稿者: 浜本 敏江 | 2009年10月13日 12:40
ソリッドスネークさん、浜本さん、コメントありがとうございます
まずは柔道ですが…実は私も1年間だけ柔道をやりました。
高校の格技の授業ですが(^_^;)
今は武道というらしいですね。
さて、柔道の場合には剣道以上に合気を意識することが重要なのではないでしょうか。
と言うのも、柔道は剣道以上に相手との関係性が技の切れに直結しているように思えるからです。
柔道では、相手の体勢が崩れいてなければ、よほどの腕力差がない限り投げたり倒したりすることは難しいですよね。
私は、相手の体勢を崩してから投げると教わりました。
(違ったらごめんなさい)
「いい組み手になる」ということは、相手の体勢が(心や体の面で)崩れていることも条件に含まれていたりしないでしょうか?
ただ、このように相手の心の状態や体の状態を呼吸を通じて読みながら立会い(柔道ではなんと言うのでしたっけ?)ができるようになる段階というのは、もう少し先の話なのかもしれません。
剣道では、勝負の歩合を第一に競う競技剣道のピークとしての「大学剣道」の時期くらいだと、ご指摘の通り「いい間合いになったら仕掛けろ」と言うことになるのだと思います。
この頃は、若さをベースに筋力を活かして「技のスピード」をあげることができるため、稽古を積んで積んで、直感的に相手の心や体の状態を察知するスピードを同時に磨くことで、せつな的に有効打突につなげることができる時代です。
大学柔道もその辺は同じかもしれません。
この時代にも、もちろん合気を考えて取り組むことで、スピードや力任せだけの技を繰り出してくる相手を打ち破ることは可能になると思います。
一流選手は、この時期特有のスピードや力に加えて、この辺りの理合を(経験的に)取り入れていたりします。
ちなみに剣道では、技を出す前には相手との間に距離があり、技自体に竹刀が介在するため、ココのところ(いい間合い)を認識するのが案外難しいです。
この日記の頃の私は、まさに日記に書いている通り、自分が相手を打つことしか頭にありませんでした。
そのため、こちらが打とうとする瞬間に多くの隙が生まれ、打とうと思っていない間には更に多くの隙が生まれていたのです。
現在は、立会いの間、相手との関係、相手の心の内、相手の手の内を読み続ける作業を継続できるように努力しています。
この作業が一瞬でも途切れたときには決定的な隙を相手に与えてしまうこともありますし、
この作業を集中して行っていても、見つけることができる打突の機会はほんのわずかであることがわかってきました。
歳を重ねていくと、スピードや力が目に見えて落ちてきます。
そうなると、打突できる機会以外に技を仕掛けていくような無駄があれば、それこそ30歳以下の若手にはスピードや力で押し切られてしまいます。
というわけで、あくまでも門外漢の私見に過ぎませんが、学生の間に「合気」について研究・実践することは大変有意義なことだと思います。
次に、浜本さんのコメントについてです。
> 小手は打てるようになった。
剣道の基本は、まず面からです。
面が打てるようになると自然とそれ以外の技は打てるようになると言われていますし、私も経験的にそれは正しいと思います。
直接見ていないので何ともいえないのですが、もしかしたら、現在小手が打てているのは、面が打てないのと同じ理由からかもしれません。
意味がわからないとお思いかも知れませんが、ありうることです。
コテはしばらく封印してメンの稽古に集中されることをおススメします。
その結果、コテも打てなくなる時期があるかもしれませんが、気にすることはありません。
メンが打てるようになれば、今度は正しくコテが打てるようになります。
> それと踏み込みがいまいちできないし、切り替えしの時、足の方が早くでてしまいます。
通常、初心者は足よりも手が先に出てしまうことを悩まれることが多いです。
もしも本当に足が先に出てしまうのであれば解決は簡単かもしれません。
剣道の打突はできるだけ自然な動きの中で行うことを目指してください。
自然な動きとは…
まず大前提として、打突は左手を中心に行います。
これは右足を大きく踏み込みながら打突することと関連しています。
右足を大きく前に出す。
歩くときのことをイメージしてみて下さい。右足を大きく前に出すときにどちらの腕を前に振り出しますか?
大抵の人は左腕だと思います(^ー^* )♪
これが自然な動きの流れです。
といっても、これが自然だと言うのはある条件があります。
それは、この動きの次にさらに動きがつながっていく前提だと言うことです。
歩くと言うのは一歩で終わることはごく稀ですよね。
右足を踏み出したら次は休まず左足を踏み出します。この動きを交互に行うことで前進するのです。この連続した動きの核は腰です。
剣道の場合、左半身に構えるため意識しづらいのですが、実は右足で踏み込んだ後に間髪いれず(歩くときと同様)左足の動きが付いてくるはずなのです。
これが「左足のひきつけ」と呼ばれる動きです。
この「左足の引きつけ」は経験者でも苦労するケースが多い部分なのですが、
歩くように剣道をすれば特に問題は起きないはずなのです。
右足と左腕を大きく前に振り出して前進するためには腰の動きが伴わなければ武利です。すると、結果的に、大きく前に振り出された右足が着地した瞬間に左足は自然と前に出てきています。
これは、左腕を前に振り出す際に柄でつながれた右拳が前方に押し出され、それにつられて右腕が前に出て行くことと関連しています。
この動きが左足の前進を呼ぶのです。
ですので、まず正面を打つときには、構えた左の拳を相手の面金の中に押し込むイメージで左腕ごと前に振り出します。このとき、できる限り両腕の力を抜いておくのがポイントです。
社会人から剣道を始めると、この腕の脱力が中々うまくいかないケースが多いのでがんばって取り組んでみて下さい。
竹刀は体が前に出る力を利用して振上げるのであって、腕の力で振り回すものではなかったりします。ウソのような話ですが、竹刀を振るだけなら腕の力はそれほど必要ないのです。腕の力が必要なのは打ち切るためです。相手の打突部位を打つ瞬間に持っている腕の最大パワーを放出する必要があります。ここで持っているパワーを最大限発揮するためにも、竹刀を振る作業の段階では極力力を温存せねばならない理屈です。
このとき良くある間違いとしては、構えた位置から右腕で左拳を上方向にいったん振上げてから振り下ろす動作を取ることです。これは避けて下さい。
これをやると剣先がいったん大きく後ろを向くので、横から見ているとすぐわかります。
左拳を前上方向に押し出すと、竹刀の柄でつながった右拳も前上方向にあがっていきます。これで剣先は十分に振りかぶれます。天井を突き上げる感じの振上げになります。
左拳を前上方向に押し出すのは、右足を同時に前方にださなければできません。
剣先は左拳が上がる高さの分だけ上方にあがりますから、右足の踏み出し具合で剣先の上がり具合が左右されるはずです。
この関係を利用して面と小手を打ち分けるのが本来の姿です。
右足を小さく前に踏み込むと左拳は少ししか前方にいけませんから、結果的に剣先は小さくしか上がりません。これで小手を打ちます。
面を打つときには剣先を相手の面の高さより上に上げねばなりませんから、その分左拳を大きく前上方に送り出さねばなりません。そのためには右足も大きく前に出る必要があります。
全ては歩くときの体の動きと同じです。
文字で説明するのは案外難しいのですが、まずは竹刀を持たずに左腕を前に思い切り振り出しながら左足で体を前に押し出してみて下さい。自然と右足は前に大きく出ると思います。
これらが体の動きの基本ですが、最後に打突の瞬間について。
これは右足が床を踏むのと、剣先が相手の打突部位を捉えるのと、メンやコテなどの掛け声を発するのとを一致させる必要があります。
これが気剣体の一致に取り組む上での初歩的な部分です。
修得するためには、まず小さな踏み込みで小さく竹刀を振ってみて声を出すことからはじめると良いかと思います。
徐々に踏み込みを大きくして、それにあわせて竹刀の振りも大きくしていきます。
床を踏むタイミングと竹刀を振り下ろして相手のメンを打つタイミングが一致するように意識してやってみて下さい。
最初は中々うまくいかないと思いますが、上手にやれている人が身の回りにいるようなら参考にするなどして工夫してみて下さい。
3ヶ月もすると効果が現れると思います。
以上、私の拙い文章を読んでいただいた上にコメントまでいただきありがとうございました。
また気が向いたらコメントをよろしくお願いいたします
お二人とも、がんばって下さい!
投稿者: 在津 | 2009年10月15日 12:29
> 武利です。
「無理です。」ですね(^_^;)
投稿者: 在津 | 2009年10月15日 12:37
僕の質問に返答頂きありがとうございます。あれから、柔道をやっていて相手の重心を見抜くことを頑張ってみましたが、何とか単純な技(支え釣り込み足、小外刈り)などは自分と同じ実力の相手には掛かるようになりました。背負い投げなどの大技はまだむりですが。
あと一つ答えて頂きたいことがあります。それは、自分より格が上の相手と対峙した時です。この場合、自分の感覚としては相手に飲み込まれ、自分が操られている気がします。相手の有利なように。この様なときに相手に飲まれないためにはどうすればよいでしょう。
投稿者: ソリッド | 2009年10月27日 19:59
僕の質問に返答頂きありがとうございます。あれから、柔道をやっていて相手の重心を見抜くことを頑張ってみましたが、何とか単純な技(支え釣り込み足、小外刈り)などは自分と同じ実力の相手には掛かるようになりました。背負い投げなどの大技はまだむりですが。
あと一つ答えて頂きたいことがあります。それは、自分より格が上の相手と対峙した時です。この場合、自分の感覚としては相手に飲み込まれ、自分が操られている気がします。相手の有利なように。この様なときに相手に飲まれないためにはどうすればよいでしょう。
投稿者: ソリッド スネーク | 2009年10月27日 19:59
> あと一つ答えて頂きたいことがあります。それは、自分より格が上の相手と対峙した時です。
> この場合、自分の感覚としては相手に飲み込まれ、自分が操られている気がします。相手の有利なように。
> この様なときに相手に飲まれないためにはどうすればよいでしょう。
難しい質問ですね(^_^;)
確かに自分より格上の相手と対峙する時、相手に遣われる感覚に陥ることがありますね。
こちらが「何とかしたい」と思ってあがけばあがくほど、益々相手の思うつぼになっていったりします。
まず、稽古の際の話の場合。
稽古の場では、このような時には、ただ無心に正攻法で懸かることです。「懸かる稽古」を心がけると良いと思います。
相手の攻めに耐えて、逃げずに攻め返し、無駄な技を出さずにこらえ、
「ここだ!」と思った瞬間に思い切って大技をかける。ひたすらこれを繰り返します。
そもそも格が違うのですから、ほとんどの場合、相手にいいようにやられます。それで良いのです。
やられてやられてやられて・・・それでもひたすら真っ向勝負を仕掛けていく。
なぜやられるのか、なぜやれないのか。常に反省してその道理を追究する。
その先に光明が見出せるでしょう。
剣道の場合には、(特に年配の)格上の先生に稽古をお願いする場合には、これにつきます。
今のは遅すぎた。今のは早すぎた。
なぜそこで打って出た?なぜそこで打って出ない?
まるで禅問答のようになっていき、悶々と悩むでしょう。
フェイントを入れて相手のリズムを外たり、変則的な技や小手先の技を出したり、力任せの技を出したり、
スピード任せに強引に技をしかければ、相手が格上であっても、ある程度運よく打つことができるかもしれません。
が、それが何になるのかということです。
武道では、本質的には得点を競っているのではないので、確率的に技が決まってもあまり意味はないと思います。
竹刀で打ち合う間接的な剣道と違って、柔道では直接相手を投げたり倒したりせねばならないわけですから、なおさら難しいことと思います。
この難しいところに挑んでいくのが、自分が格上に達するための第一歩です。
次に、試合などの勝負がかかった場での場合。
これは稽古と違って何とかしなければなりません。
勝負をするからには、相手が格上であろうが格下であろうが勝たねばなりません。
柔道をやっていないので、きちんと答えになるかどうか自信がありませんが、
なんとか答えてみますと・・・そのとっかかりは、おそらく「勝とうとしないこと」だと思われます。
相手の有利に運ぶとき、こちらが勝ちに行くところを逆にやられていたりしていないでしょうか?
こちらは相手が勝ちに来るところをやることができているか。
そこは互いに勝ちに行かない。ギリギリの忍耐勝負をするしかありません。
これが両者の格を分けるところだと思います。
もちろん、勝とうとしないかわりに、決して負けてもいけません。
「さぁ、どこからでもかかって来い。少しでも心か体が崩れれば、間髪いれず打ち倒しますよ。」と、
そんなこちらの負けん気と相手の負けん気でせめぎあえれば互角でしょう。
相手が格上に感じると言うことは、その心境になれないということではないでしょうか。
相手の攻め気に押されて、苦しくなって技を出しているから「飲まれている」と感じるのではないかと推察しています。
飲まれないためには、同様の気迫で攻め返すしかありません。
武道では、相手の攻め気に対して技で応じれば九分九厘返り討ちにあいます。
攻め気に対しては攻め気で応じ返し、ギリギリのところで互いの技がぶつかる形を作る必要があります。
そこの道理をおさえて、とにかく辛抱することです。
できるできない以前に、もはや勝負の場に踏み込んでいるのであれば、そこは「やるしかない」と覚悟を決めるべきでしょう。
負けに不思議の負けなしと言うように、負けている理由は明らかです。
互いに勝ちをおさめることができる機会はそれほど多くはないはずです。
その一瞬を捉えるために、お互いにひたすら辛抱するしかないのです。
この感覚を養うために、日頃の稽古では一本でも多く格上の相手に稽古をお願いする必要があると思います。
そこでこの「攻め気」が養われるのだと思います。こればかりは体得するしかありません。
攻め勝って後に技を出す。
剣道ではそんな姿を目指していますが、柔道ではどうですか?
以上、あまり参考にならないかもしれませんが、私の考えるところを書いて見ました。
お互いに道を究めるべくがんばりましょう!
投稿者: 在津 | 2009年10月27日 23:10
お久しぶりです。今日も道に迷ってここに書き込ませてもらいました。
今日は学校の中で練習試合をやったのですが、始まってものの5秒で投げ飛ばされました。自分よりも30キロぐらいは軽い相手にです。悔しいですが、これは勝負なので嘆いてもしかたありません。
お尋ねしたいのは試合の取っ掛かりの瞬間、10秒経過するまでの気持ちの持ち方というこです。今日は先の先を取って、一本背負いか、小内刈りで投げ飛ばそうと思いましたが、逆に相手に先の先を取られてしまいました。一瞬何が起きたのか分かりませんでしたが、自分の不用意の行動が一本負けを招いたのだと感じました。気迫で負けたつもりはありません。これは試合始めの心の持ち方が問題だと感じました。慎重すぎてもダメ、勢いがありすぎてもダメ、どう気持ちを持てばいいのか分かりません。分かる範囲で回答してもらえると嬉しいです。
投稿者: ソリッド スネーク | 2010年06月03日 21:17
お久しぶりです。がんばっておられるようですね♪
ご質問の件ですが、これは剣道でも共通の課題に思えます。
書かれている通り、慎重すぎても勢いがありすぎてもダメでしょう。
ではどうするのか。
結論から言えば平常心で臨むことです。
これこそ「言うは易く行うは難し」ですがそれしかありません・・・。
相手を投げてやろうとか技を決めてやろうとか考えてはいけません。
ただ、攻撃してくる相手の好きにさせてもいけません。
平常心で相手を見定めることから始めなければいけません。
目の前にいる相手の今その時の状態を掴むこと無しに何をすべきかの答えは得られません。
稽古の際には応じ返されようと逆に先を取られようと、ひたすら自分が先をかけることを目指して攻撃的に技を仕掛ければ良いと思うのですが、試合ではそうもいきません。
技を決められるということは命の危険に陥ることですから不用意に向かっていくことはできないはずです。だからといって臆病風に吹かれればますます不利になります。
相手の攻撃的な気をいなして不戦の状態を維持しつつ観察することから始めて、互いに機会を伺ううちに相手がこらえきれず攻撃しようとする、その先を取って確実に技をかけるということです。
相手との実力差がどれくらいあるかにもよりますが、同等以上の相手と対戦する場合、まず合気になれなければ敗北は必至です。
合気を作れなければ先を取られる危険が高まります。
合気を作れたとしても、こらえきれずに闇雲に技を仕掛けていけば、応じ返されたり起こりを取られたりするでしょう。
まずは合気の状態を作るまでに遅れをとってしまわない様に、相手が技を出そうとすればいつでも相打ちで応じるつもりで、先を許さないことを意識して試合を進めます。
剣道では通常は相手と2段以上の差があると(実力があるのに段位を取得してない場合を除いて)、難しいことをしなくても先を取って力技で一方的にしとめることができます。
そこはおそらく柔道でも同じではないでしょうか?そうでない限りそうそう簡単に先はとれません。
そこで、次に試合開始と同時にやるべきことは、相手の今その時の実力を感じ取ることです。
先を許さない気持ちを維持して機会があればこちらが先を取る気持ちで攻め続けるのは当然ですが、相当な実力者や苦手なタイプの相手に不用意に技を出してはいけません。
いずれにせよ機会は一瞬です。そこ以外では技は決まらないのですから、その機会を攻め合いの中で見極める作業を繰り返す必要があります。
逆に相手が辛抱できず不用意に技を出してくるようなら、その先を取って技を出すのは比較的容易です。
何をきっかけに技を出してくるのかを見極めて相手の心理を突いて崩します。
ここの所の心の余裕が大事です。
開始早々に技を決めるのは本来お互いに至難の業のはずです。
そこを理解して試合を進めればそれほど容易に技を決められることはなくなると思います。
逆に自分が技を決めるのも難しいことを理解しておくべきです。
ここを理解せず、不用意に自分から技を決めに行けば、逆に相手にとっては思う壺になりますので要注意です。
やるべきことをやって後の勝敗はそれほど気にするべきものではありません。
その試合では相手が強かったと言うだけのことです。
しかし、試合は稽古で身につけた内容を試す場ですから、あまりに不本意な試合内容の場合には日頃の稽古の質を見直す必要があるかもしれません。
とにかく、武道は試行錯誤です。
やられてやられて、やられた悔しさをばねにして、同じ失敗を繰り返さないように工夫研究を重ねて行けば必ず何かをつかめるはずです。
まずは試合巧者の試合運びを研究したり、彼らの話を謙虚に聞いたりすることをおススメします。
お互いにがんばりましょう!
投稿者: 在津 | 2010年06月18日 10:30
一昨日、柔道の試合がありました。試合には負けたけど己には克ちました。その代償に膝を破壊されましたが。
気の働かせ方や駆け引きに関して、今まで管理人さんには質問して来ましたが、今日は試合や乱取りの前の気持ちの持ち方について質問があります。一昨日、試合をしたさいに私はチームの期待を一心に背負い、名誉な事に予選ではなく団体の準決勝に出してもらいました。私はあの時、頻呼吸になって体が震えるほど高揚していました。今までやった事を決死の覚悟でやればいいと考えながらです。死んでも、何があろうとも負けない。そんな気分です。後から、試合内容を後輩に評価してもらうと今までで一番アグレッシブだったそうです。
しかし、私は東京医大の相手に内股で一本を取られ、チームの負けを導きました。気が緩んでいたはずはなく、試合は技ありと有効をそれぞれ取っていたのにです。私は武道家として何か重大なミスをしているようでなりません。
投稿者: ソリッド スネーク | 2010年08月10日 01:21
試合、残念でしたね。
実際に会場で見たわけではないので、あれこれ言うのは筋違いな気もしますが、思い当たることを書いてみます。
まず、試合の流れはどうだったでしょうか?
> 試合は技ありと有効をそれぞれ取っていたのにです。
ということは、試合は最後に一本を取られて逆転されるまで有利に進んでいたのではないでしょうか?
であれば、試合の流れに乗ることに失敗しているのかもしれません。
有利に試合を進めている場合、一番注意すべきは捨て身の技です。
相手は時間の経過と共に苦しくなり、残り時間が少くなると大技で逆転を狙うしかなくなります。
その様な場面ではますます冷静になることが必要です。
全力で試合の流れを掴み、掴んだら冷静にその流れに乗り、相手が無理をしようとするところを逆にしとめる。
相手が無理をしないようならその流れのままこちらも無理をしないで進む。
ここで注意すべき点は消極的にならないことです。
冷静に戦うことと消極的になることは同じではありませんが、
多くがここで間違えて冷静になるべき所を消極的になり、
結果的に受け身となって却って逆転を許してしまいます。
そして、根は同じ話ですが、展開が有利になった勢いを借りて猪突しないことです。
展開が不利になった相手は、より積極的に攻めてきます。
こちらも不用意に攻撃を強めれば逆転を許す危険が高まります。
もともと機会は試合の中にほんの少ししかなく、その一瞬をつかめるかどうかのデリケートな勝負をしているのですから、
こちらから相手に機会を与えるようなことをしないことです。
消極的にならず、猪突せず、常に先をかけて試合を最後まで支配し続ける。
それが目指す姿なのかなと思います。
特に団体戦ではチームの勝利がかかってきますので、冷静な試合運びは不可欠です。
常に勝利を信じて不敗の境地を追究する。
よく言われるように、今回の負けにも不思議はないと思われます。
逆転負けを喫した原因を考え抜いて、同じことを繰り返さないように稽古を積む。
最後は稽古あるのみです。
お互いがんばりましょう♪
投稿者: 在津 | 2010年08月10日 12:31
ご丁寧な返事ありがとうございます。
自分は大きな試合も終わり、今は練習のない夏休みなのですが、全てが終わってゆっくり考えると、あの時にもうこれで勝ったという慢心があったと思います。自分の不覚です。その辺りの練習が足りない事を痛感しました。アドレナリンや優勢な試合運びがあっても油断してはいけませんね。後から、聞いたのですが、自分の相手は東京医大のキャプテンだったようで、相手に気迫で負けたのかなと思います。
大胆かつ慎重に、それが冷静さなのでしょうか。
投稿者: ソリッド スネーク | 2010年08月15日 13:32
冷静さ、それは乱取りなどの中で意識しながら練習するものなのでしょうか。それこそ、相手に強烈にぶつかりながらも無理な動きや、隙のある動きをしないなどでしょうか。
投稿者: ソリッド スネーク | 2010年08月15日 13:44